強い木枯らしが、赤ちょうちんの火影をマチコの格子戸に揺らせている。
だが、週末の通りはいつになく賑やかで、5人、6人と連れ持って歩くサラリーマンたちが、コートの襟を立てつつ急いでいた。
「年末ボーナスの平均はちょっと上がったそうだし、忘年会も増えそうね。みんなの予定はどうなの?」
小窓から見える光景に、真知子がおでんを皿によそいながら言った。
カウンター席には澤井と松村、そして水野の横で、上京したばかりの津田が夕刊を開いている。
「俺は、もう2つ終わった。昨日はカラオケ歌いすぎちゃって、喉が辛いんだよ。ほら、声が変だろ」
ほろ酔いの澤井は顔を赤らめながら、横に座る松村に同意を求めた。
「う、う~ん。澤井さんの歌を聴かされてる方も辛いと思うけどなあ」と、松村が冷やかした。
真知子は「ぷっ」と吹き出し、以前、常連たちとカラオケに行った時、やたらめったら最新のニューミュージックを1本調子で咆えていた澤井を思い出した。
「へん!お前に言われたかないよ。広告マンのくせして、古臭いフォークソングばっかり歌いやがって」
口を尖らせる澤井は、ギターを抱えるふりをして茶化した。
「仕事と歌の趣味は、関係ないじゃんか!フォークソングは、俺の哲学なの。誰かさんみたいに、女の子のウケ狙いだけの軽薄なセンスじゃないんすよ」
「何だよ。言いたい放題、言ってくれるじゃないか!」
いつになく興奮する澤井が、松村の肩を掴みかけた時、「よしなよ。カラオケのヘタウマで喧嘩するなんて、一番くだらないよ」と水野がたしなめた。
しかし、鼻息を荒くしたままの二人に、とうとう津田の声が飛んだ。
「ほんま、“目くそ、鼻くそを笑う”やなあ。ワシに言わせたら、どっちも“味噌が腐る”レベルやったわ。あっ……この言葉、古いな。腐ってんのは、わしも同じやな」
津田の一人ボケとつっこみに、真知子がおでんの皿を出しながら「あははっ!」と笑った。してやったりとばかり、津田が目じりをほころばせた。
澤井はしばらく口をつむると、「ったく、また津田さんにイイとこ持ってかれちまったよ」と苦笑いした。松村は「う~ん、オヤジギャグを超えたジジイギャグ。寒すぎまっせ~」と関西弁で返した。
カウンターに笑顔が戻ると、真知子がふいに口を開いた。
「私、津田さんの演歌……大好き。上手じゃないけど、いい味してるのよね」
真知子の言葉に、水野は冷酒を飲み干して頷いた。
「うん……あれは、語るような唄だよ。人生が滲み出てるような。津田さん、どうやってあんな歌い方を?」
水野の質問に、澤井と松村も興味津々の顔で耳をそばだてた。
「そない、たいそうな練習なんぞしてへん……わしは、メロディーよりも歌詞に興味を持ってましてな。それも、四十過ぎてからやなあ。若い頃はあんたらみたいに、昭和の流行歌が好きやった。演歌なんぞは嫌いやった。それが、だんだんと好きになった。演歌の詩を読んでたら、いろんなもんが見えてきたんや。歌詞の裏に隠れてる哀楽ちゅうか、人生ちゅうか、自分に重ねるようになった。ほなら、死んだ親父やお袋の気持ちが実感でけるようになった。わしは、何も分かってなかったなぁと涙が出た……それで、演歌を歌うようになったんや」
語りべのような津田の言葉が、ふーっと吐き出されたタバコの煙に溶けていった。
「……私も最近、演歌が好きになりました。2年前、父が亡くなった後、残っていた古い演歌のレコード盤を整理してて……見つけたんです。レコード盤の袋に書かれてた、歌についての父の感想を。ちょうど、今の私ぐらいの歳に書いたようでした。それで、レコードをかけてみました」
遠い目をしながら、しかし口調はしっかりとする水野の横顔を、真知子や澤井たちが見つめていた。
「ほぅ……どないでした……ええもんが、見えましたか?」
津田がぬる燗の盃を口にしつつ、優しげに笑った。
「ええ……父の感想を読んで、目をつむって歌を聴いてると、子どもの頃に叱られたことや、青年になって反抗した時、たぶん父はこんなふうに思ってたんだろうなと、その心もようが分かりました。父の私に対する厳しい姿勢は、私が息子に接する形とはまったくちがいますが、我が子を想う気持ちは何ら変わらない熱いものだと実感しました」
水野の声に津田は「うん、うん」と何度も頷き、こう言った。
「そのレコード……あんさんのお父さんが、いつか聴くやろ、読むやろと思うて、置いてはったんかもしれませんなあ。まぁ、そない思えると、歌の味もぐっとようなりますなぁ」
水野は、津田の顔をまばたき一つせずに見ていた。そして、その言葉が終わると「はい……」と声を詰まらせた。真知子は、さりげなく冷酒の瓶を傾けた。
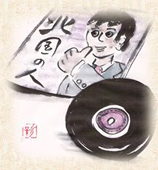 しんみりとした雰囲気が満ちた店内に、松村の声が響いた。
しんみりとした雰囲気が満ちた店内に、松村の声が響いた。
「ふーん、四十歳を過ぎると、そうなるのか。じゃあ、澤井さん、もうすぐだね。でも、あんな歌が好きなんじゃ、隠されてる心もようなんて分からないよ」
松村が、澤井の肩をポンと叩いた。
「てやんでぇ、俺は裏表の無い歌が好きなんだよ。だから、心の澄んだ人間ってことなんだよ」
澤井が腹をポンと叩いて答えると、すかさず松村がつっこんだ。
「そうかなぁ。単に人間が薄っぺらで、スケスケなだけじゃないの?」
またも勃発しそうな二人のやりとりを、真知子たちの笑い声が包んでいた。
