ほのかにふくらんだ桜の蕾を、春の夜風が揺らしていた。
毎年のことだが、この季節は、マチコの通りに流れてくる料理屋の匂いがぬるんだ空気に乗って、鼻腔を刺激してくる。
その向こうからは、ある言葉がよく聞こえるのである。
「栄転、おめでとう!」と送別会での音頭が響き、「ようこそ本社へ!」と歓迎の声がして、サラリーマンたちの宴は大いに盛り上がる。
真知子は、そんな言葉を耳にすると、ふと、これまでマチコで出逢っては別れた客たちの顔を、走馬灯のように思い浮かべてしまうのだった。
「あの人、どうしてるかしら……」
ついこぼした言葉に、ぬる燗の純米酒をかたむけていた澤井が「おっ! 出た出た!」と突っ込んだ。
真知子お手製の“桜漬け”を肴にする松村は「真知子さん、これ作る頃になると、毎年そうつぶやいてんじゃん」と答えた。
「……言われてみれば、そうね。今日だって、その桜漬けのこと、美味しいって喜んでくれた人を何人か思い出してたの。何となく、センチメンタルだわ」
そう言った真知子の視線が、厨房の戸棚に向けられた。
すると、聞き覚えのあるしゃがれた声が、玄関から聞こえた。
「ほんで、次の真っちゃんの行動パターンは、忘れ物の棚をいじり始める。うっほほ! お見通しやで」
「あっ……あら、イヤだ。私って、ワンパターンなのね」
真知子は、棚の戸に伸ばしていた右手の動きを止めた。
「でもさ、その棚の中の忘れ物って、何が多いの?」
澤井は棚の中を覗いたことがないらしく、腰を浮かせながら真知子に訊いた。
真知子は、なにげなく戸を開いた。
「やっぱり、タバコとライター。時たま、お財布や腕時計もあるけど、それはちゃんと取りに来てくれるから……このペンは塚田君のね。今度帰って来たら渡すわ。それと、この手帳は長野の加瀬さん。もう随分来てないから、送るって電話したけど、こっちへ行く理由にしたいから置いといてって。このコンパクトは、私の悪友の島崎理恵。あの子も、子育てで大変だから、もう化粧なんてかまってらんないのかしら」
あれこれと忘れ物を手にしつつも、真知子は懐かしげに目を細め、その表情を見つめる津田もやけに嬉しそうだった。
「そのボール? 何だよ、それ?」
松村の指さした先に、薄汚れた硬球ボールがあった。
「あんたの上司。ほら、元・甲子園球児の小野山さんの忘れ物。2月に、草野球チームの仲間の人たちと来たの……小野山さん、変わったね。とっても楽しそうだったよ」
真知子は次々と、忘れ物にちなんだこぼれ話を披露した。
今度は澤井が、「その赤い袋は?」と顎を動かした。
「あっ、これは越中薬仙堂の樋口君。あの子、置き薬屋なのに、頼んでない薬まで置き忘れちゃってさ。だから、これはそのまま使ってないの」
「樋口君かぁ、あそこの煎じ薬と俺の実家にある比良山の薬草が、よく似てたんだよねぇ。彼、どうしてっかなぁ」
松村が目をつむって、樋口の思い出話を始めると「ほら、みなさいよ。あんただって」と真知子がたしなめた。
「ふむ……忘れ物には、それぞれ物語があるもんや。それに忘れ物をしとるっちゅうことは、マチコとその人が、まだ赤い糸でつながってるわけや。こうやって聴いとると、下手なドラマ見てるよりもええ話やなあ~。ぐっと酒も、美味しいなるわ」
ニンマリとする津田は、松村の桜漬けを一つもらって、盃に浮かべた。
「でも……一番私が気になっているのは、これなの」
真知子が手にしたのは、何の変哲もない白い盃だった。
「どこの誰の忘れ物か、思い出せないの。うちの盃に似てたから、一緒に片付けちゃってね。だけどよく見ると、ちょっとイイものみたいなの」
ぼんやりと白い盃のツヤは、確かにマチコのものより上品で、その肉が薄く、とても軽そうだった。
物欲しげな顔で松村が「高そうだね、それ?」と訊いた。
すると、澤井が「白磁じゃないの?」と目利きした。
「まっ、どんなもんでも、ええがな。……わしは、こう思いたいな。それを忘れた人は、きっとワザと忘れはったんや……またマチコに来たい。そう願をかけたんや。その内、現れるで」
上機嫌になってきた津田が、澤井の酌を受けつつ語った。
「う~む、いいっすねぇ。それこそ、マチコのロマンですねぇ」
澤井の言葉を受けて、松村が真知子にほほ笑んだ。
「本当にそうなったら、真知子さん、超感動しちゃうでしょ!?」
真知子は、ふっと顔をほころばせた。
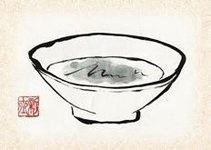 「実はね……前にも一度、そんなことがあったの」
「実はね……前にも一度、そんなことがあったの」
「本当!? すごいじゃん! いつのこと、それ誰なの?」
澤井と松村が同時に声をハモらせると、真知子のおだやかな視線が津田のシワ立った手元を見つめていた。
「わしは……初めてマチコへ来た日に、このマイ盃を忘れて帰ってなぁ♪」
嬉しそうな津田の返事と真知子たちの笑い声が、いつまでも、ずっと、赤ちょうちんの向こうで揺れていた。
(了)
